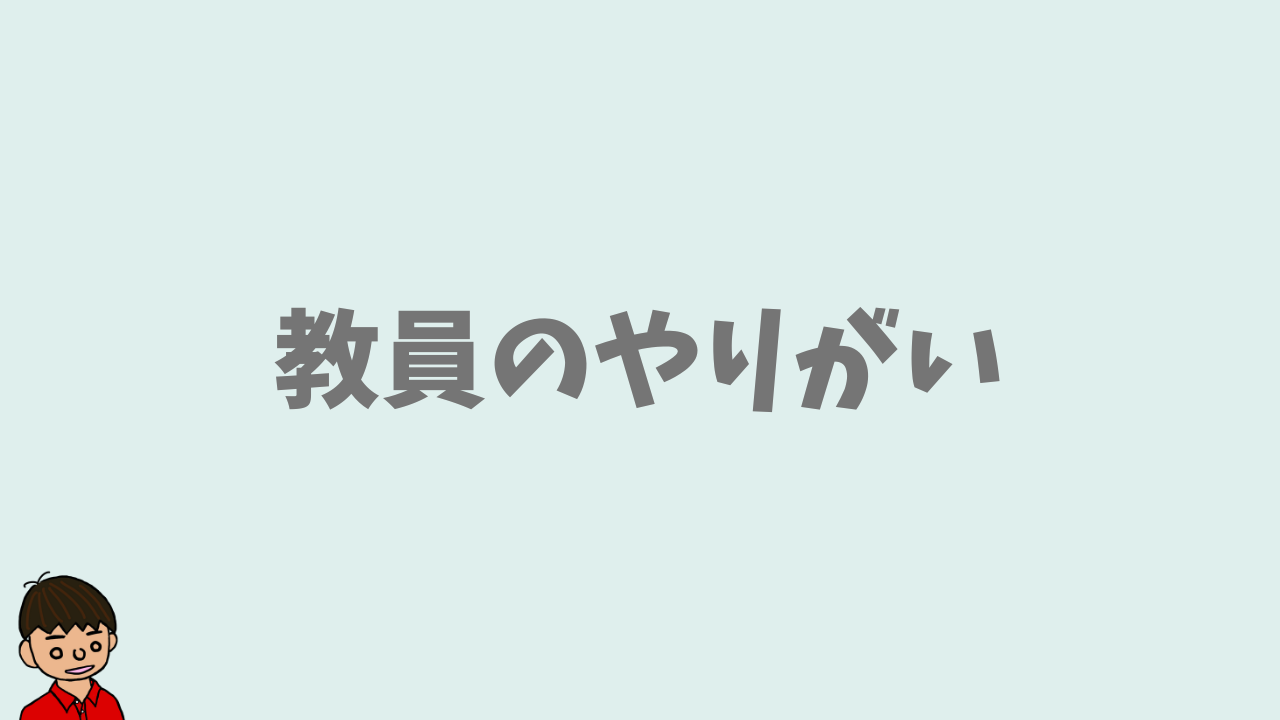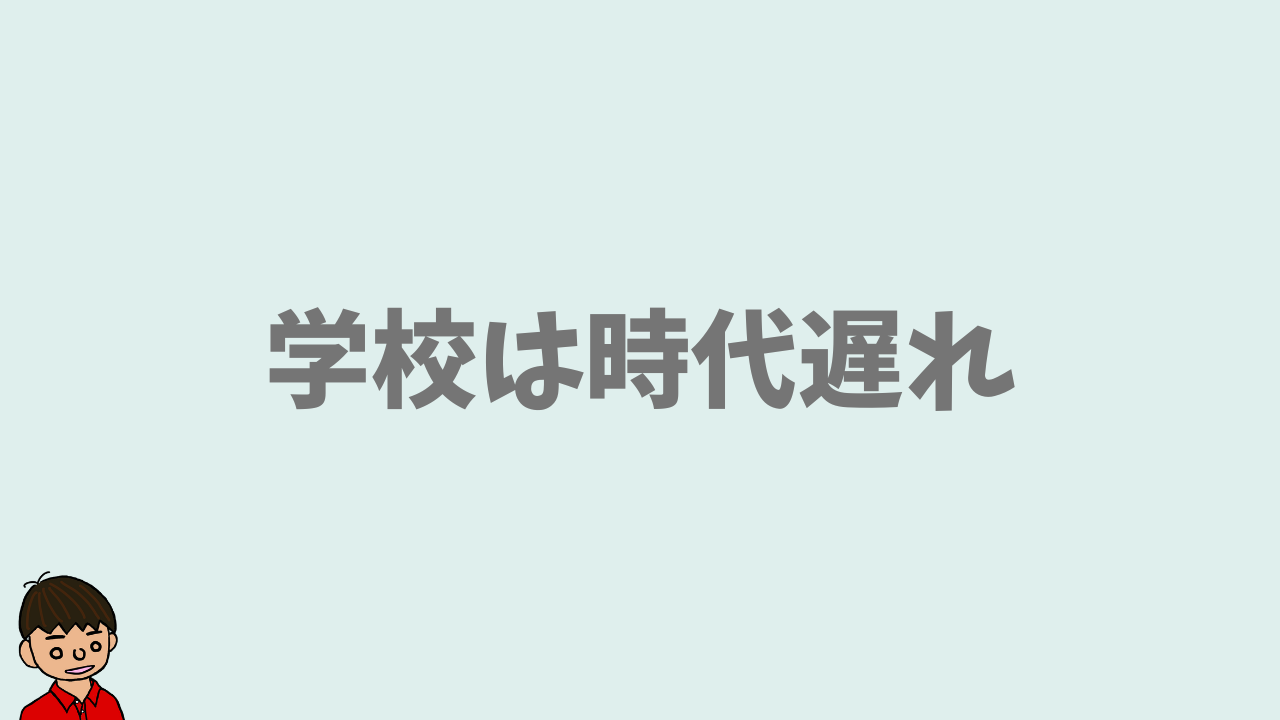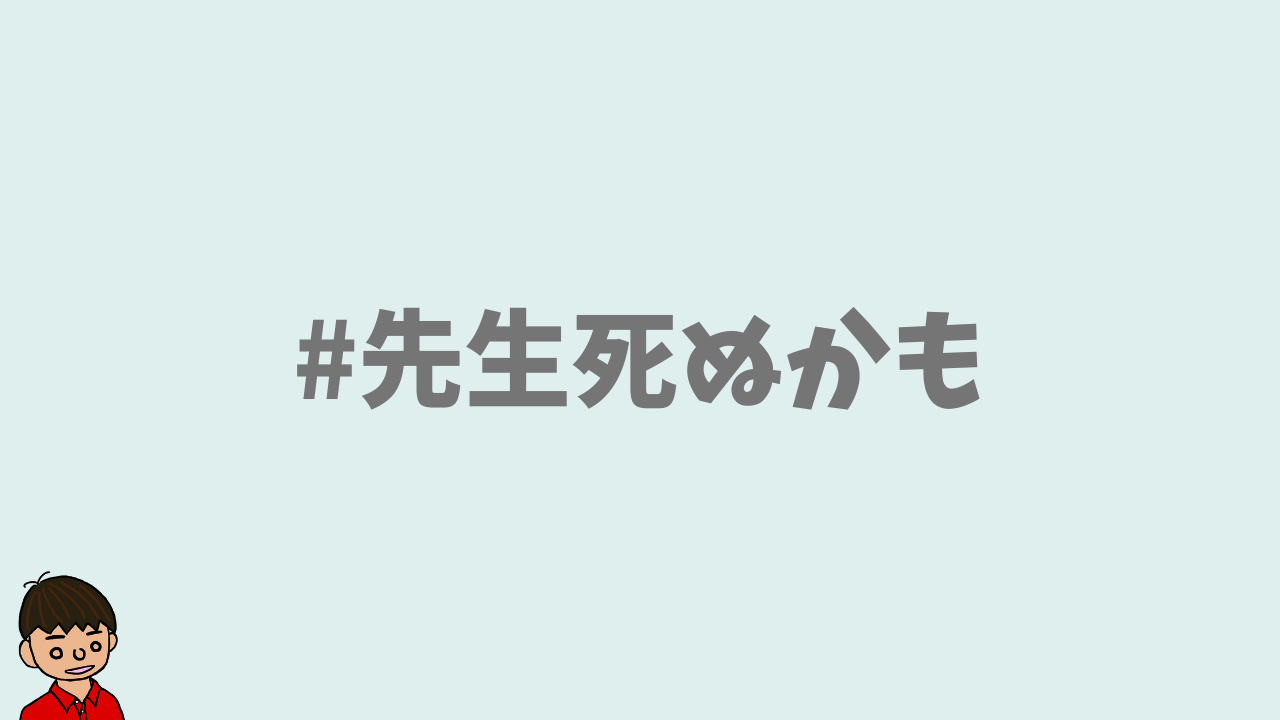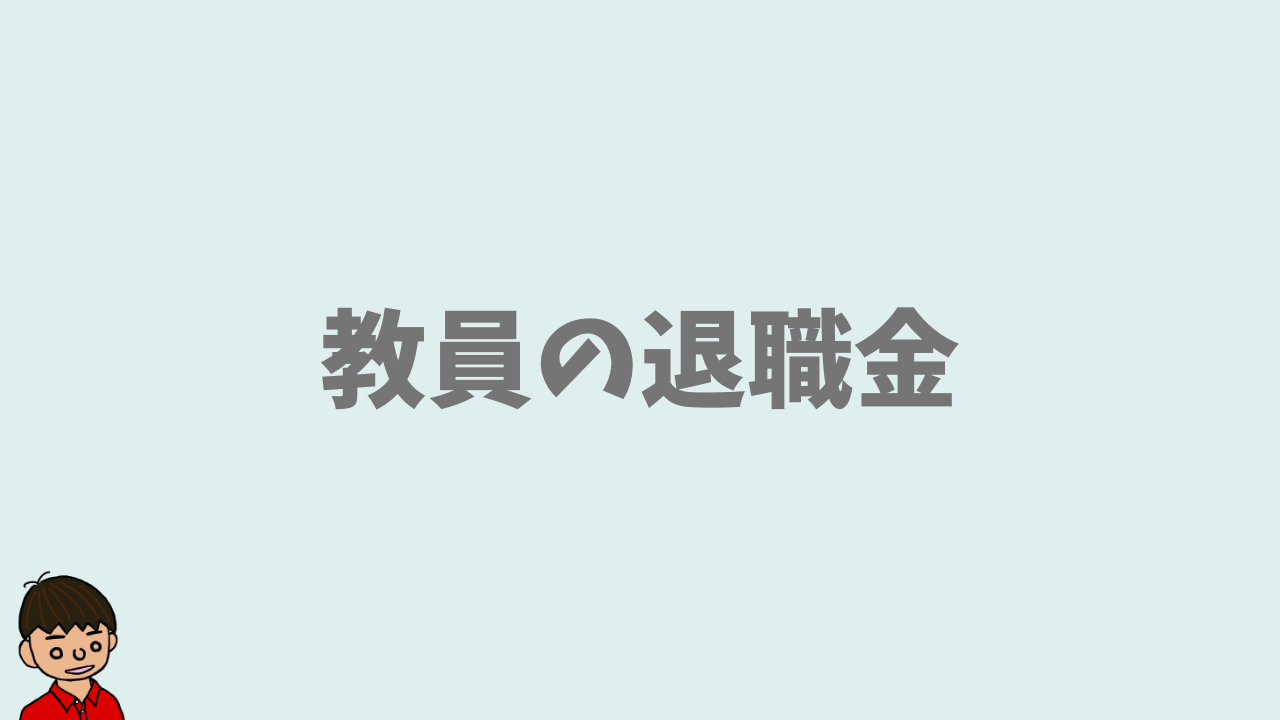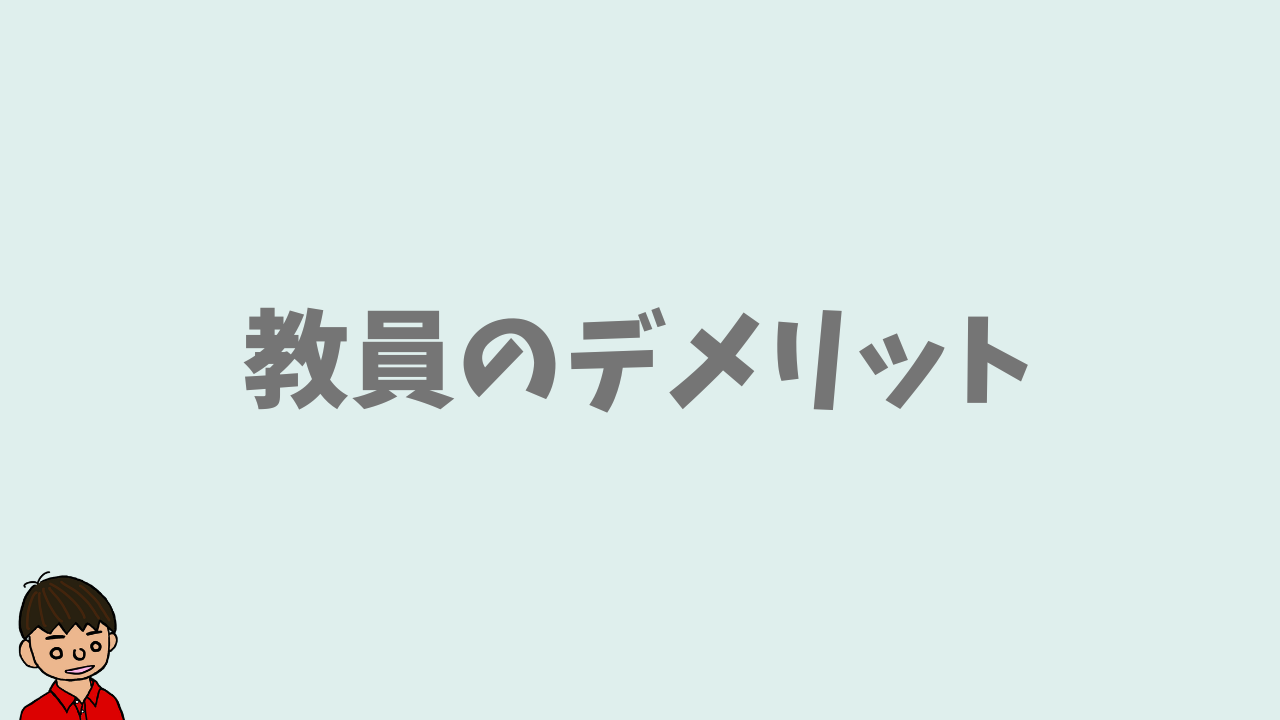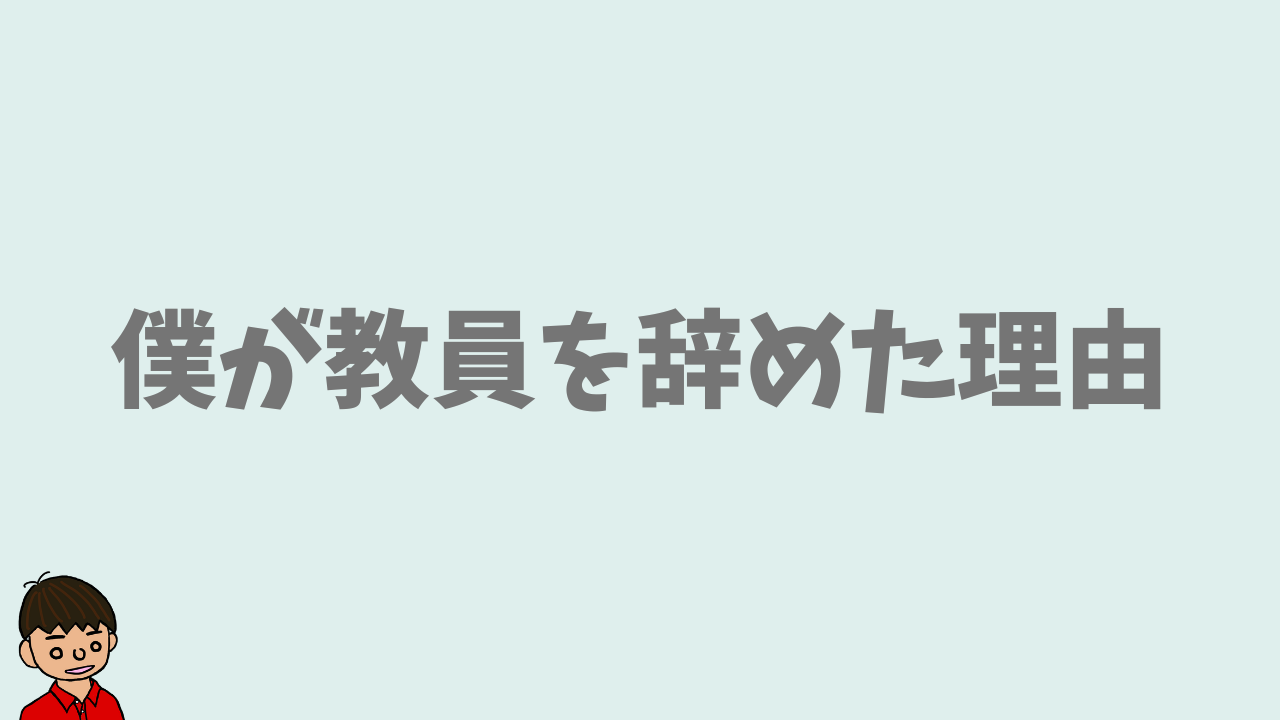教員採用試験不合格者が担任?「講師で担任」の理由と問題点を元教員が解説
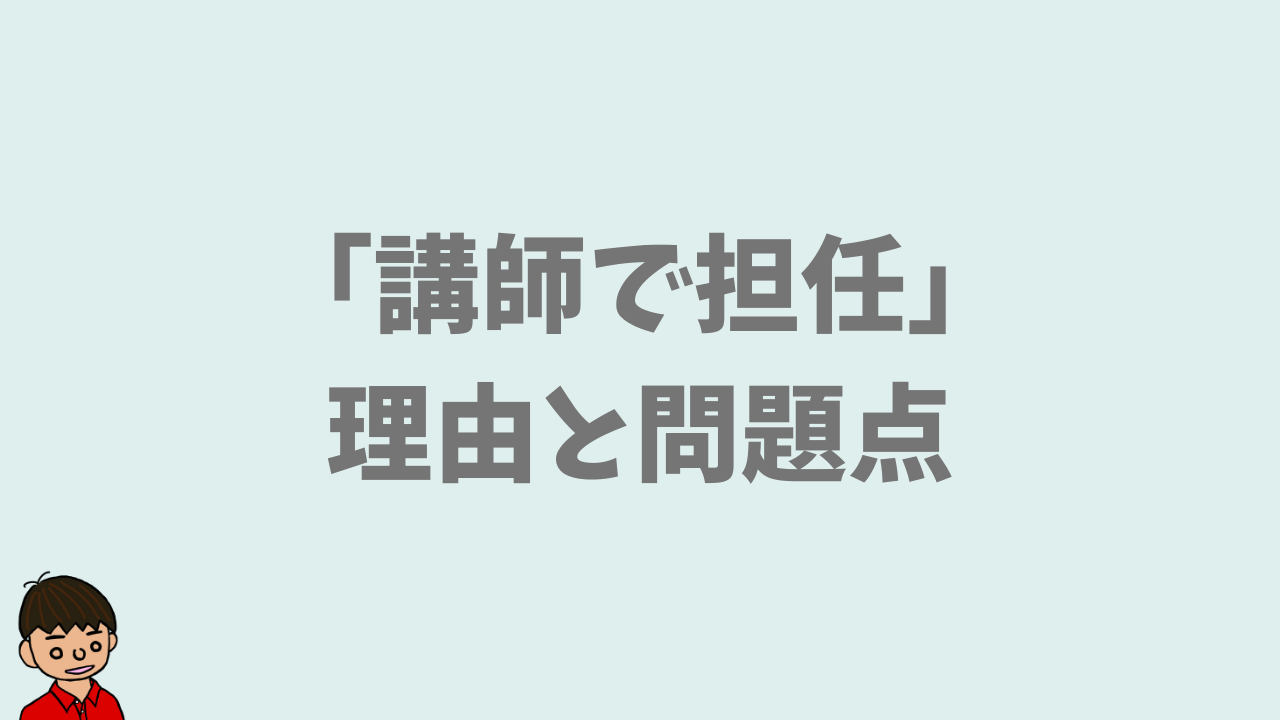
学校の現場では、
「教員採用試験で合格になった人が担任をもたないで、
教員採用試験で不合格になった人が担任をもつ」
っていうことが、わりとあるんですよね。
そこで本記事では「講師で担任」の理由や問題点について説明をします!

「講師で担任」はおかしな話
(常勤)講師が担任になるのって、おかしな話なんですよね。
そもそも講師とは?

学校の教員は、正規採用かそうでないかによってざっくりと2つに分けることができます。
| 教諭 | 正規採用 ※教員採用試験に合格 |
|---|---|
| 講師 | 非正規採用(臨時的任用職員) ※教員採用試験に合格はしていない |

学校の教員って「先生」ってひとくくりにされるけど、実際には教諭と講師が(7:3くらい?の割合で)入り混じっています。
講師は、さらに大きく2つに分けられます。
| 常勤講師 | フルタイムで働く講師 |
|---|---|
| 非常勤講師 | フルタイムではなく、授業の「コマ」ごとの時間契約で授業をする講師 |
非常勤講師が担任になることはほぼほぼないと思うので、この記事では常勤講師の話をします。
まずは常勤講師の人はどういう理由で常勤講師になるのか?について。
講師になる理由

講師になる理由は大きく2つあると思います。
| ①望んで講師になる | (例) ・家事があって正規採用されるとキツイから、教員採用試験は受けないで講師を続ける |
|---|---|
| ②しかたなく講師になる | 教員採用試験で不合格になった人が、教員採用試験の勉強をしながら講師として働く |
こんな感じで2つの理由があるんですけど、①の「望んで講師になる」っていうパターンはわりとレアです。
実際には②のパターンがほとんどです。

僕自身も学校現場に入った1年目は②のパターンでした
「講師で担任」のおかしさ

つまり、こういうことです。
「講師で担任」=教員採用試験で不合格になった人が担任になっている
これだけだったら、「正規採用の教諭だけでは担任が足りないからなのかな」って思うかもしれません(実際、小学校の場合はそういうこともあるようです)。
が、学校現場を見てみると「教諭が副担任」っていうことも結構あるんですよね。
採用試験に合格した教諭→副担任
採用試験に不合格の講師→担任
おかしくない!?

教員1年目の僕は、
「なんで不合格だった僕が担任なの?合格した教諭が担任をやればいいんじゃないの?」
って思っていました。
ほんと何も知らなくて純粋(=ある意味アホ)だったと思います
まあ実際には、「家庭の事情で(拘束時間の長い)担任はできない」っていう理由で副担任になっている人もいます。
が、必ずしも全員がそういうわけではなさそう・・・
なんで講師が担任になるのか?

どうやら、学校現場の厳しい状況が理由としてあるみたい。
※これは僕自身の体験談じゃなく、単なる推測です。
「講師で担任、教諭で副担任」の疑問の答えは
「教諭だけだと『担任をできる力を持っている人』が足りないから」
だと思います。
っていうか、そうじゃないとつじつまが合わないですよね。
そうじゃなきゃ、教諭そっちのけで不合格だった講師に担任をやらせるわけがありません。
「教員採用試験に受かったんだから、担任できるんじゃないの?」って思うかもしれませんが・・・そんなことはないです。
そもそも教員採用試験で受験生(未来の教諭)について完璧に判断できるわけではありません。だって、ペーパーテストと面接、模擬授業で試験をしているだけなので。
だから、
正規採用してから「あ、この人に担任をやらせるのは厳しいな…」ってわかる
ことがあって、
かといって公務員だから首を切るわけにもいかないし…
っていうことになっている
としか思えません。
つまり、こういうことです。
1つの学校に配置される教員の数は決まっている
↓
学校によっては、担任をできる教諭が足りないってことに
↓
担任の穴を埋めるために「講師で担任」という切り札を使う
めでたしめでたし!・・・
おかしいでしょーが!!!
だったらこうすればいいじゃん

じゃあ、もっと試験で合格者数を増やして教諭を増やせばいいじゃん!って思うかもしれません。
つまり、「教諭の増加」という対処法。
ですが、これは微妙です。
というのも、少子化の進行で「必要になる教員の数」は減っていく以上、採用数をしぼらざるを得ないからです。
じゃあ、「教員採用試験で合格になった人だけど、担任をやるのが厳しい人」を育てて担任をできる力を身につけさせればいいじゃん!って思うかもしれません。
つまり、「教諭の教育」という対処法。
僕は「”教員の教育”を絶対にやるべき!力がない人を副担任にしてずっと放置するのはおかしいでしょ!!!」って思ってるんですけど、
現場で「講師で担任」という切り札が使われまくっていることを考えると、「教諭の教育」という対処法は機能していないっぽいです。
「教諭の教育」が機能していない理由として考えられるもの
| ①教諭自体に限界がある | ・どうやったって担任をできる力を身につけられない人が教諭になっちゃったパターン ・担任をそもそもやるつもりのない人が教諭になっちゃったパターン |
|---|---|
| ②教諭を育てる気がない | ・初任研などの研修で「担任をできる力」を伸ばせていない ・学校現場で上司が教諭を育てようとしていない |
いずれにせよ、「講師で担任」という切り札を使わざるをえない事情が学校現場にはあるっていうことです。
「講師で担任」の問題点
そんな「講師で担任」には問題点があります。
①研修がない

講師には研修がないんですよね。
正規採用されて教諭になると、初任者研修(初任研)というものを受けることになります(1年かけて)。そこで一応「学級担任」についても学びます。
※まあほとんど効果なんてないと思うけど
ところが、講師にはそういう研修がないんですよね。
学校現場の上司からのサポートがあるとはいえ、「右も左も分からない」状態でいきなり担任をやることになります。

実際、僕は「新卒1年目で、講師で、担任」だったのですが、、、
「わからないことがあったら聞いてね!こっちからは何も教えないから」っていう感じで結構つらかったです。
(まあ、やりながら学んでいくしかないと思うので、「わからないことがあったら聞いてね」以上でも以下でもないとは思いますが・・・)
②教員採用試験に支障が出る

担任をやると教員採用試験に向けて勉強する時間が減ります。
担任をやると仕事量は半端なく増えて長時間の残業もあたりまえになりますが、担任をやっている以上「講師だから早く帰れる」ということにはなりません。
そうすると試験勉強できなくなるんですよね。

実際、「講師で担任」っていう切り札を使われて担任になった人が業務に追われて勉強できずに不合格・・・っていうのを見たことがあります。
(まあその人の勉強不足なのかもしれませんが、本当につらそうにしていたので、しかたない部分もあったと思います)
僕自身は「来年の試験は面接だけでOKですよ」っていうパターンの講師で「合格率はほぼ100%」って噂されているパターンの講師の分類だったので、負担はほぼありませんでした。
が、もし普通に試験勉強をしなきゃいけない立場だったとしたら、、、マジできつかったと思います。
関連:教員採用試験の体験談を元教師が赤裸々に告白する【落ちた】
③1年で異動になることが多い

講師は1年契約なので、来年度も担任を続投することが原則できません。
担任をやってせっかく生徒との関係が深まっても、1年で終わりです。
伝えたいこと
担任の穴を埋めるために「講師で担任」という切り札を使う
ってのは
絶対におかしい!
管理職・教育委員会が「あ、この人に担任をやらせるのは厳しいな…」って判断した人をずっと副担任にして担任をやらせないのは
絶対におかしい!
志がある人材を見限るなよ!
なに戦力外みたいな扱いしてるんだよ!!
ちゃんと育成しようよ!!!
以上でーす