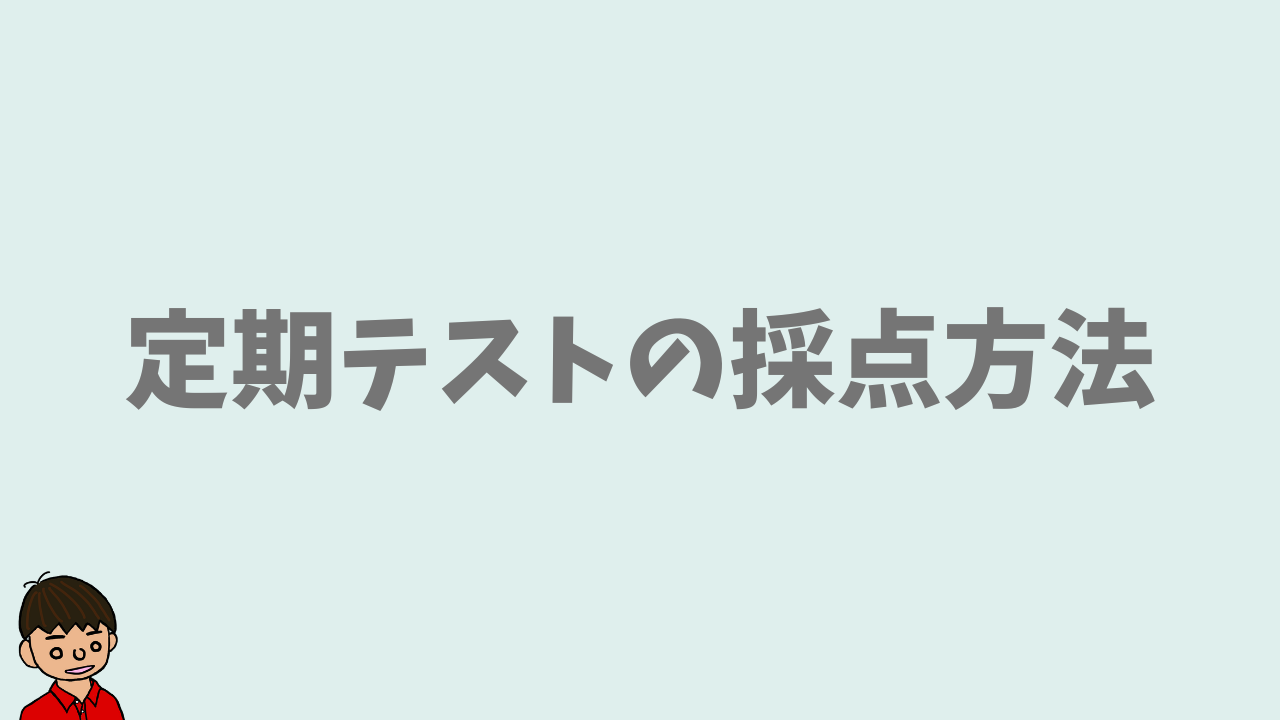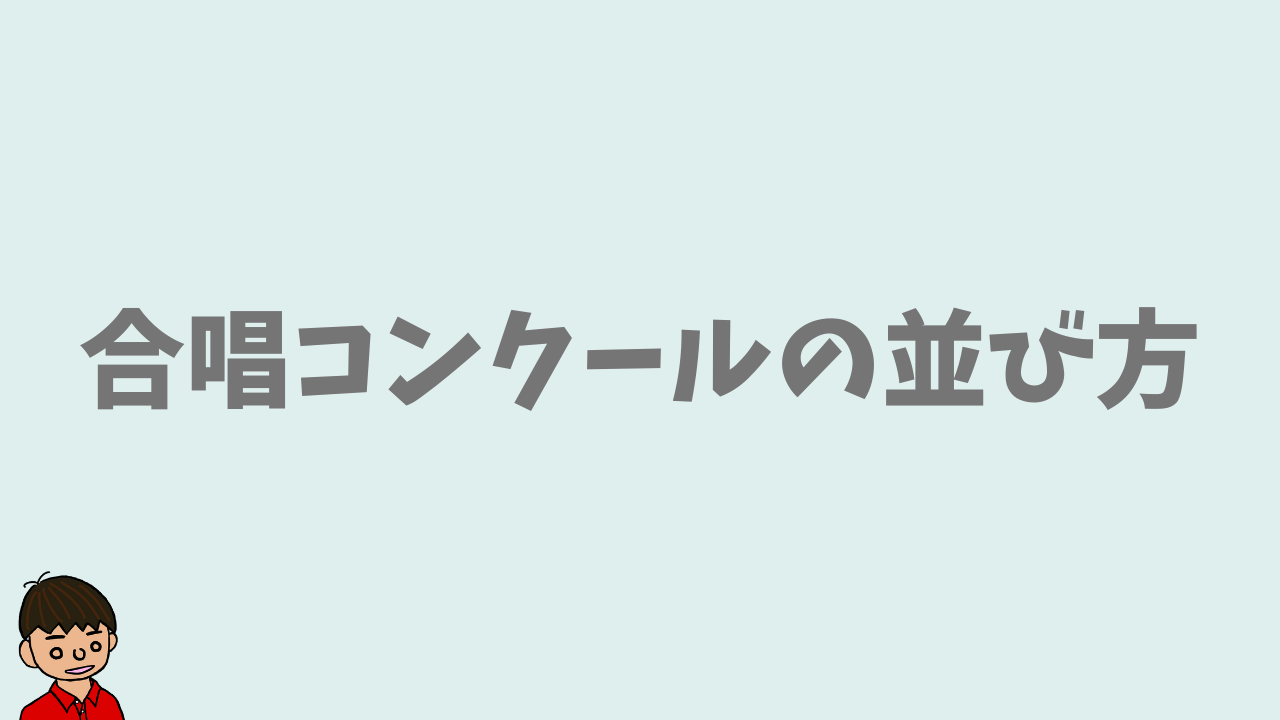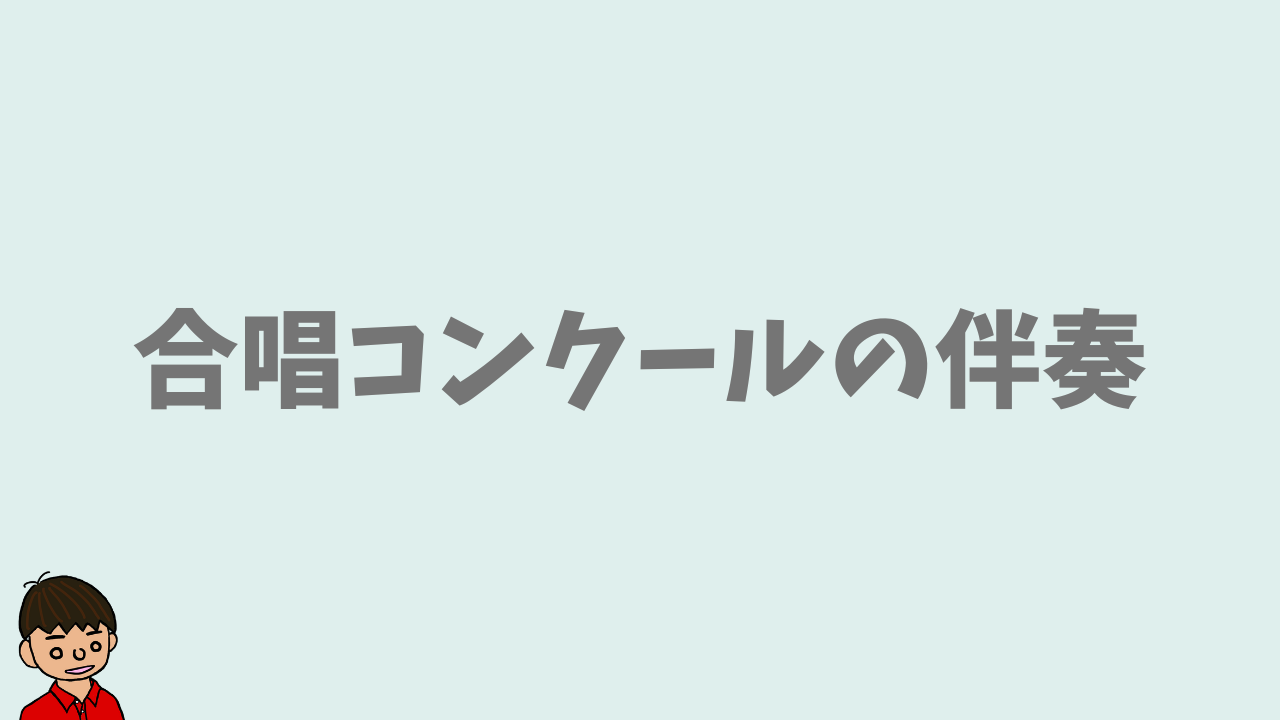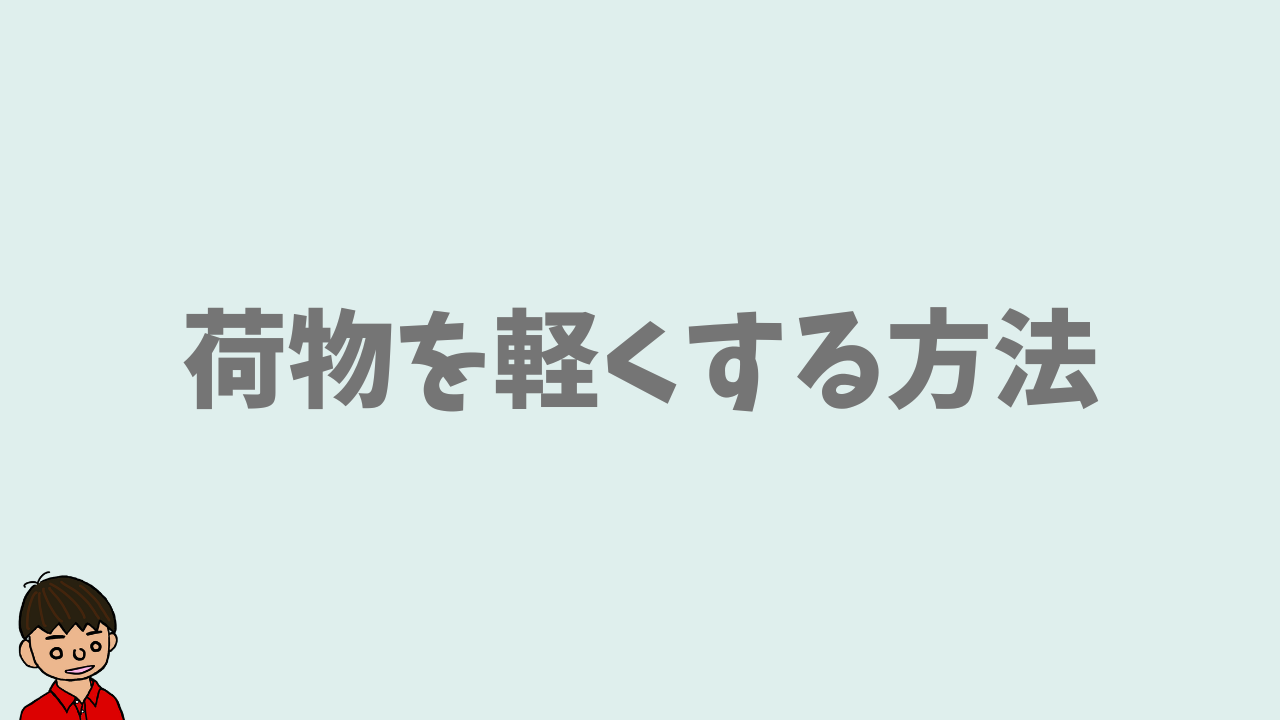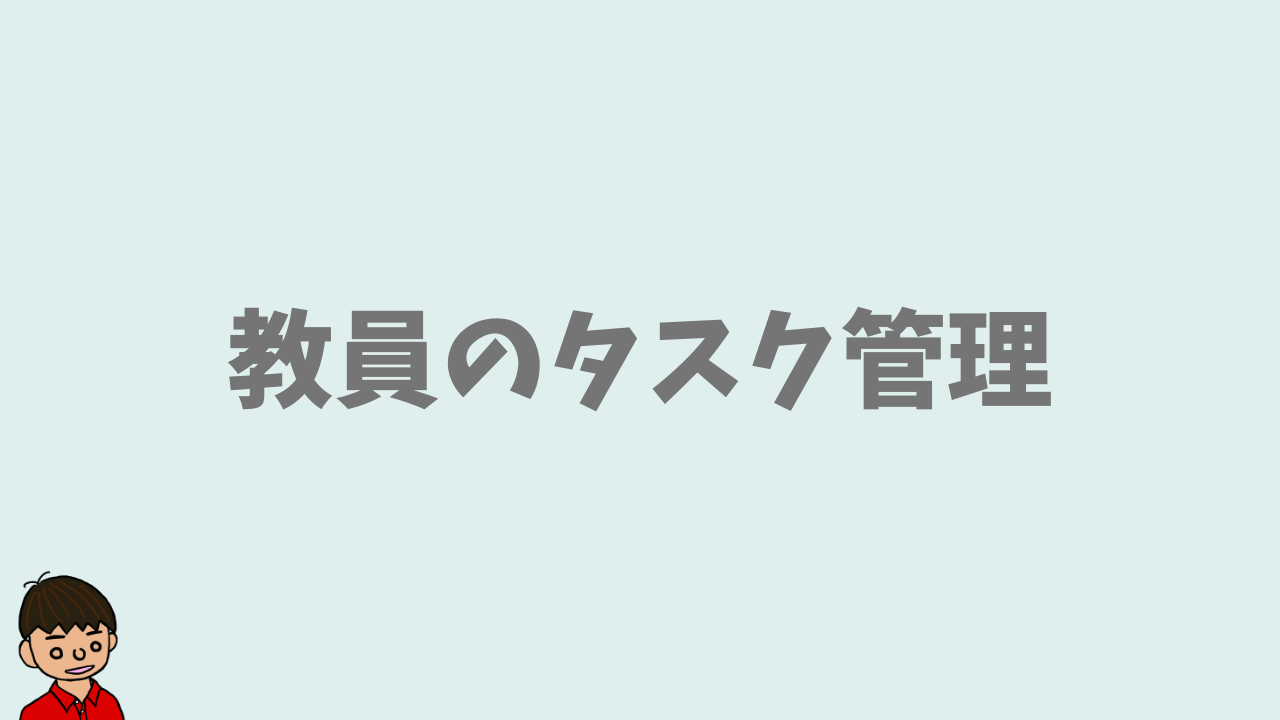教材研究・授業準備のやり方【授業準備が間に合わない教員の方へ】
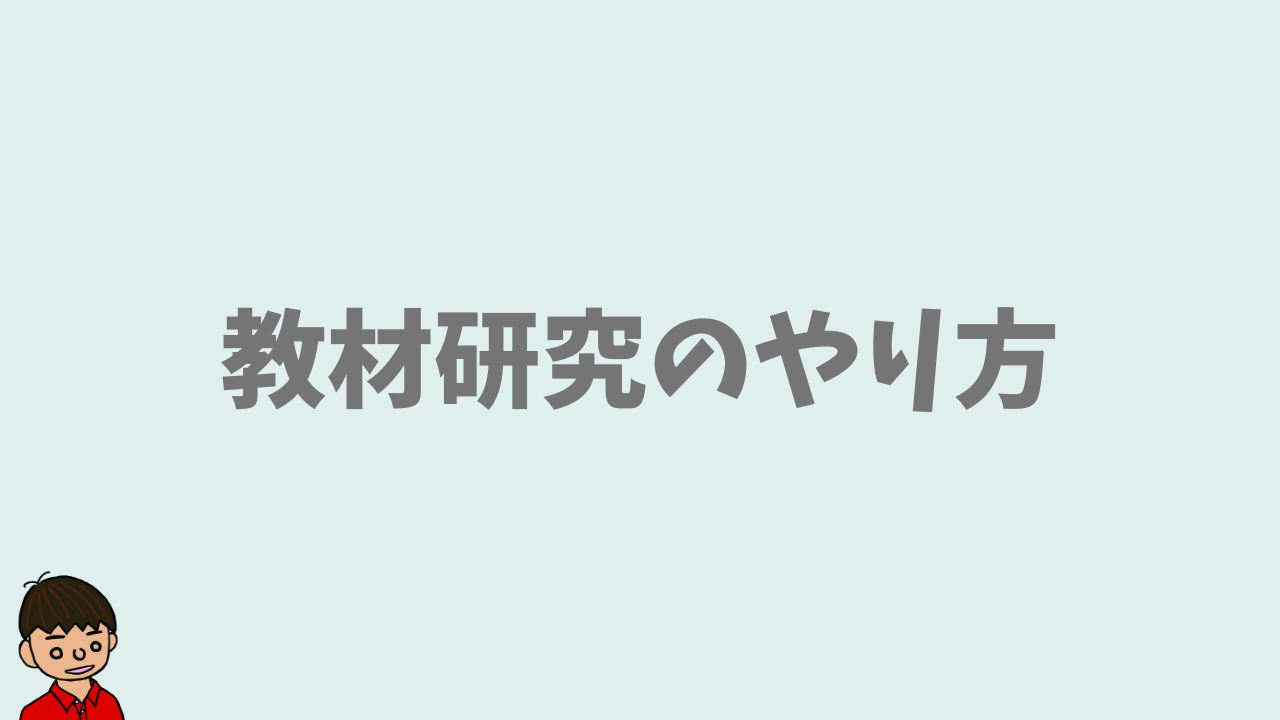
教材研究・授業準備のやり方(進め方)について、元社会科教員の僕の経験をブログ記事に残しておきます!
元教員の一つの事例にすぎないですが、よかったらお読みください!

現場の現実
なにかしら工夫をしないと授業準備なんてできない…!ってのが学校現場の現実。
授業準備の時間が取れない理由
- 一日にこなさなきゃいけない校務多すぎ
- 若手だからってたくさんの仕事を振られる
- なのに空き時間少なすぎ
- 突発的にトラブルが起きて時間とられる
- 保護者からクレームが入って保護者対応に追われる
- 放課後は部活指導と下校指導
- すべて終わって職員室に戻ってきたらデスクの上に書類が山積み
- 先輩や用務員の人の世間話、長話に付き合わなきゃいけない
教材研究・授業準備をしないと地獄

授業準備をしないと二重に地獄。
生徒も地獄:「眠い・・・」「わからない・・・」
↓
それをみた教員も地獄:「眠そうにしてるわ・・・」「顔にわからないって書いてある・・・」
で、焦ってギャグを言ったりして授業を盛り上げようとすると、
友達同士、無言で顔を見合わせて「つまんな…」って言われるのがオチです。
残り30分もあるのに「はやくチャイム鳴ってくれ」って感じる地獄のような授業になる
教材研究・授業準備は必須!!!
教材研究・授業準備をする時のスタンス
教材研究・授業準備は沼
教材研究・授業準備って明確な「終わり」がないんですよね。いくらでもやれてしまう。
やればやるほど楽しいんだけど、逆に、どこかでケリをつけないとシンドくなりがち。良くも悪くも沼なんです。
高校の教員だったら、もしかしたら沼にはまってもいいのかもしれません。高校はあまり生徒指導に時間を割かなくても大丈夫なことが多いし(※学校によるけど)、教科の専門性が求められるので。
一方、小学校・中学校の教員は教材研究・授業準備の沼にはまらないようにした方が良いと思います。
小学校・中学校は毎日のように生徒指導が頻発するので、教材研究・授業準備の沼にはまってしまうと仕事が終わらない→睡眠時間が減ることになりがちだから。

もちろん「教員は教えるプロなんだから〜」っていうヤツ(キレイゴト)はわかっていますが、
そんなこと言ってらんないくらい勤務時間内に授業のことを考える時間がないのが現場のリアルだし、そもそも小中レベルなら教科の専門性はそれほど求められないし。
ってことで、沼にはまらないようにする!…って意識することが大事だと思います。
100点を求めない
意識としては、100点満点の教材研究・授業準備をしよう!っていう感覚を捨てるべし!ってのが僕の考えです。

僕自身、教員になりたての頃は「深く・細かく教材研究をして、自分がいまできる最大限の授業をしよう!」って思っていたんですけど、
時間的・精神的に追い込まれてかなりシンドくなった経験があります。
っていうか、余暇の時間や睡眠時間を削って頑張ったとしても、”全生徒”の学びが深まる「100点満点の教材研究・授業準備」なんかできないんですよね。
んで結局、タイムリミットが来て、自分の中で「まだ不十分なんだよなあ…」っていう悔しい・申し訳ない感覚で授業をするという。精神衛生上、マジで良くないです。
しかも、頑張って教材研究・授業準備をして教員的に「これは完璧だああ!!!!」って思える授業をしたとしても、生徒の学びにつながるとは限りません。
例えば、直前の授業が体育の水泳とか持久走だった場合は、みんな疲れ果てて社会科の授業どころじゃなくなるわけです。これが学校の残酷な現実。
まあもしかしたら「直前の授業は水泳だから、今日の授業はこうやってやろう」ってところまで考えるのが究極の授業準備なのかもしれないけど、、、そんなことやってたら時間がいくらあっても足りないと思います。
それに実際は見学の生徒もいるわけだし、生徒によって疲れの度合いも違うし。
つまり何が言いたいかというと、
「100点満点の教材研究・授業準備をしよう!」って思うとシンドくなるだけだし、
そもそも「100点満点の教材研究・授業準備」は教員の自己満足にすぎなくて、それが生徒の学びにつながるかどうかは別の要因によって大きく左右されるんだから、
100点を求めるのはやめよう!
ということです。
70点を目指す
70点を目指そう!くらいの感覚で良いと思います。大体でOK。

授業をやった結果、生徒が「わかりにくいです」っていう意思表示をそれとなくしてきたら、その部分の教材研究を改めてやって補強すればいいんです。
んで、次回以降の授業で訂正・バージョンアップする。
学校の授業は週に何回もあって「やり直し」ができるんだから、その利点を活かさないのはもったいないです。”最終的に”生徒の学力が上がればいいわけですし。
あと、教員がそういう姿勢(試行錯誤・アップグレードする姿勢)を見せることが、「学ぶとはどういうことなのか?」を生徒に伝えることにもつながると思います。
とはいえ、マジメな教員はつい完璧主義に陥りがち。
授業も何もかも適当にやって、公務員としての安定した身分に安住しているダメな教員もいますが、
この記事を読んでくださっている方は、頑張ろうと思っている教員のはず。そういう教員はわかってるのに沼にはまっちゃいがち。
そうならないようにするために、
教材研究・授業準備に時間制限を設ける
のが良いと思います。
例えば、「この授業はぜっっっっったいに2時間で作る!」って決めるとか。
2時間たったら、どれだけ不十分な教材研究・授業準備だったとしても切り上げる。で、授業に突入する。
自分自身で「終わり」を決めて、沼にはまらないようにする。
教員はそういう働き方をしないと、いつまでたっても帰れません。ムリしすぎて体を壊しちゃダメ。もうあなたは十分頑張ってるんだから、ムリしなくていいよ!って言いたい。
授業準備が間に合わない人へ
教員が授業準備をうまいことやる方法は、ざっくり2つに分けられます。
- 授業準備の時間を生み出す
- 授業準備の時間を短くする
①授業準備の時間を生み出す

1つ目の方法は、「授業準備の時間をなんとか生み出す」です。
- 他の仕事を減らしたり
- 他の仕事にかかる時間を短くしたり
して、授業準備の時間をなんとか生み出すしかないんです。空きコマの時間を増やしてもらうことはできないので。
僕が実際にやってみて、効果が高かったなと思ったのは5つ。
- (1)掲示物作成をやめる
- (2)提出物を出席番号順で集める
- (3)鋼のメンタルで飲み会を断る
- (4)授業時間中の「生徒の活動の時間」を増やす
- (5)時短グッズを使う
(1)掲示物作成をやめる
思い切って掲示物作成をやめました。
教室の掲示物って、いくらでもこだわれるんですよね。教育効果が大きいのか謎なのに。
どう考えても授業準備の方が大切です。

僕も初任の頃は凝った掲示物を作ろうとしていましたが、すぐに断念しました
2年目からは割り切って「掲示物に力を入れない」と決めたら、掲示物に関する仕事量が一気に減りました!
関連:教室の掲示物は頑張らなくていいと思うし、工夫しなくていいと思う
(2)提出物を出席番号順で集める
提出物を回収する時、あとで教員が出席番号順に並べ替える・・・ってことにならないように、最初から出席番号順で集めるようにしました。
(3)鋼のメンタルで飲み会を断る

飲み会は断りまくりました。

上司から指導もされましたけど、「授業準備の時間を生み出すために断っているんだから、悪いことをしているわけじゃない」って思っていました
(4)授業時間中の「生徒の活動の時間」を増やす
授業中の生徒の活動の時間を増やしました。
50分の授業の大半を「教員からの説明」の時間にしてしまうと、授業時間中にフリーになれず苦しくなりますよね。
なので、「授業時間中にフリーの時間を作る」ためにも、なるべく生徒の活動の時間を増やす!
で、「生徒の活動の時間」中にやれる仕事をやる!という感じです。(もちろん生徒を完全に放置はしないようにしながら)

「教員からの説明」の時間って、説明をコンパクトにすれば結構短くできるはず
(というか、質問できる時間を長くとった方が良い場合もあると思う)
(5)時短グッズを使う
ハサミ、ホッチキス、印鑑ホルダーなどなど、地味だけど時短になる便利グッズを使うのも便利でした。
関連:教員におすすめのiPad
②授業準備の時間を短くする
教員が授業準備をうまいことやる方法の2つ目は、「授業準備の時間を短くする」です。

授業準備の時間をなんとか生み出そうとしても限界があるので、授業準備の時間自体を短くしないとどうしようもないんですよね。
僕が実際にやってみて、効果が高かったなと思ったのは2つ。
- (1)プロ講師の授業のマネをする
- (2)形に残す(ストックする)
(1)プロ講師の授業のマネをする
スタディサプリっていうオンライン学習サービス(授業動画が見放題になる有料サービス)に登録して、授業を見て、プロ講師の説明の仕方・話し方のマネをしました。
※本当は中学生・高校生向けのサービスだけど、大人でも登録できる
※スタディサプリに登録すると、約15分に区切られた授業動画(小学校〜高校)を全教科見放題になる
スタディサプリの良いところは、説明がコンパクトでわかりやすいっていうところ。
(自分の説明にムダが多すぎることがわかる)
僕の使い方はこんな感じ↓
スマホを使って通勤電車の中で見る
↓
「なるほど!こうやって説明すればいいのか。同じように説明してみよう」って考えておく
↓
プロ講師のマネをして授業をする
結果、学校の生徒に「わかりやすかった」って言われることが増えた・・・気がする

月額約2,000円のサブスク出費はちょっと痛いけど、授業準備の時間が減って授業もうまくなるなら必要経費ってことで我慢できる!って思いました。
※月額約2,000円は少し躊躇する値段なので、「14日間の無料体験」を利用して使用感をチェックしてみるのがおすすめ。イマイチだったら無料体験期間中に解約すればOK
スタディサプリについてくわしくはこちら↓
関連:スタディサプリを大人が使うメリット・デメリット【社会人の学び直し】
(2)形に残す(ストックする)

来年度以降の授業準備の時間を短くするために、授業準備の成果を形に残しました。
講義ノートでも授業プリントでも、なんでもいいので形に残します。

形に残す作業自体が大変かもしれないけど、
形に残しておくと、その学年の授業を再び担当した時に圧倒的に楽になります!
メモも残さず頭の中だけで考えて授業して終わり・・・だとストックされていかないので、しんどいままに。2回目以降でも、「どうやって授業したかな?」って思い出さなきゃいけない
僕はiPadで(Apple Pencilも使って手書きなどで)作成して全部デジタル化していました。電子化した方が便利だと思います。(「あの授業のメモはどこだっけ」って探さなくて済むので)
社会科の教材研究・授業準備をしたい人は社会科ブログもぜひチェックしてみてください!
教材研究・授業準備の流れ

ここからは、教材研究・授業準備の具体的な流れについてです。

僕はこんな感じでやっていました。
①学習指導要領をチェックして、達成目標を確認する
「この単元でできるようになってほしいこと」(=達成目標)を明確にします。
たいていの場合、学習指導要領にちゃんと書いてあるので、それをチェック。
(チェックしていない教員が結構多い気がする)
②その目標を達成するために用意されている素材=教科書を見る
達成目標を確認したら、教科書をパラパラとめくりながら眺めます。
んで、「ここわかりやすい!」って部分を確認すると同時に、
「あー、ここわかりにくそうだな」「字数の関係で省略してるなあ」って感じで、生徒がつまずきそうな部分の見当をつける。
③達成目標に応じた課題を作る(定期テスト、レポート等)
学習指導要領に書かれている達成目標にマッチしていて、かつ教科書を使えば達成できるレベルの課題を作ります。
僕は単元末にレポート(授業時間内に一気に書かせる形式)を課すことが多かったので、定期テストだけでなくレポートも作っていました。
各回の授業を考える前に作る、というのがポイント。
④課題を達成するための単元構成を練る
その課題をクリアするために、授業は何回必要なのか?どの内容をどれくらいの時間かけてやるのか?などを考えます。
あくまで予定。実際に授業をやってみて、生徒の状況を見て調整することは多々ありました。
⑤各回の授業を考える
単元構成を練ったら、いよいよ各回の授業を考えます。
「単元末の課題(レポート等)をクリアするために必要なこと」を授業で扱う、という感じ。
各回の授業を具体的にどうやって作るのか?については、また別記事で説明します。
伝えたいこと
教材研究・授業準備は沼
教材研究・授業準備は70点でOK
授業がうまくいかなかったら次回以降の授業で訂正・バージョンアップすればOK!
以上でーす
教員におすすめの記事
教員の仕事効率化についてまとめた記事はこちら